地域との連携
10月9日、10日に1泊2日の日程で三重県津市に行ってきたので、学校を留守にした。東海・北陸地区連合小学校長会教育研究三重大会に、東海北陸7県から800人以上の校長が集まった。13の分科会に分かれて、教育課題について協議を行った。
令和8年度の研究大会は福井県で行われ、磐周地区で「社会との連携・協働」をテーマに発表する。1年以上前からの校長への宿題である。分科会の趣旨や研究の視点をまとめるのが、私の担当である。
自分なりのアイデアをためている段階だが、牧之原市の竜巻被害と以前に読んだ本の内容が、頭に影を落としている。
2014年刊行の増田寛也氏による「地方消滅 - 東京一極集中が招く人口急減 (中公新書)」は、自治体に衝撃を与えた。
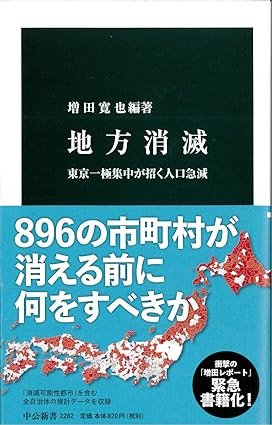
増田氏が「消滅可能性」を指摘したのが、静岡県では、熱海市、伊豆市、下田市、御前崎市、牧之原市の5市と、東伊豆町、松崎町、西伊豆町、川根本町の4町である。消滅と言っても、地上から煙のようになくなるわけではない。人口減により財政事情が悪化し、インフラや公共サービスの維持が難しくなるということである。教育とて例外ではない。
牧之原市は、竜巻被害からの復興を始めているが、前途は厳しいのではないか。能登地震からの復興が遅れている状況を見ると、人口減の地方都市の再建は、後回しにされるのではないかという疑念がわく。だから某国会議員の「運のいいことに能登で地震があった」という発言が、被災者の心情を逆なでしたのであろう。子供たちの成長は止まってくれないのだから、教育環境の整備と復興は、最優先に行ってほしいと願う。
令和元年から令和5年5月まで続いたコロナ禍を経て、少子化が急加速した。小学校入学児童が減り、低学年から順に学級数が減った。今後は、複式化や統廃合が課題になってきている。2021年度から2023年度の3年間で、廃校・閉校した小学校は全国で1000校以上だったという統計がある。2024年度以降も年470校ほどが廃校になっている。
文部科学省が「社会に開かれた」「地域にともにある」学校を推進しようとしても、学校のパートナーである地域が、悲鳴を上げかねない状況にある。地域コミュニティの核になるような人材が育ちにくい状況では、「コミュニティー・スクール」や持続可能な社会(地域)の維持も難しくなる。
小学校は、今ある教育スタイルを維持し続けることは難しい。地域との連携を模索しながら、校長として新しい学校像を示すことが必要だと思う。地域コミュニティーと公教育の協働をもとに、校長として創意ある教育活動を提案することを、「研究の視点」に盛り込みたいと考えている。
環境教育
花壇のコスモスが花を咲かせています。去年よりも茎が高くのびています。



環境教育
本校敷地の西側の崖は、土砂災害警戒区域となっている。崖の下には民家が並んでいる。法面には草が生い茂るのだが、草刈りの作業が危険なので、2年前に防草シートを市で張ってくれた。
ところが、クズが上に横に下に茎を伸ばし、暴走している。樹木の上の方までからみつき、葉を広げている。秋の七草の1つである「クズ」は、セイタカアワダチソウの侵入を拒むほどで、最強である。



研修
校内運動会が近づいてきました。子どもたちは元気で、昨日も今日も欠席は全校で1名だけです。
登校の様子を見守り、子どもたちに話しかけていると、こんな声が何人かの口から聞こえてきます。今日は、2時間目に全校で縦割りリレーの練習があるのです。
「リレー、やだ。」「走りたくない」「運動会ゆうつ」
教員は運動会に向け、子どもたちを盛り上げ、追い立てていくのですが、誰もが皆、運動会を楽しみにしているわけではないことを忘れずに、声掛けをしていけるといいです。
急に走るのが速くなる魔法やひみつどうぐがあるわけではありません。阪田寛夫(さかた ひろお)さんの「びりの きもち」という詩は、子どもの心の声を代弁してくれています。教師は「びり」の子に共感し、寄り添う態度が大切だと思います。本校の先生方は、PBSを意識して「びり」の子にどんな声を掛けるのでしょうか?
びりの きもち
さかた ひろお
びりのきもちが わかるかな
みんなのせなかや 足のうら
じぶんの鼻が みえだすと
びりのつらさが ビリビリビリ
だからきらいだ うんどうかい
まけるのいやだよ くやしいよ
おもたい足を 追いぬいて
びりのつらさが ビリビリビリ
園と小学校との接続
4年生といっしょに笠原こども園へ行ってきた。今回は教育実習生も誘った。保健室もなく養護教諭もいない園の様子を見てもらいたかったのだ。
園庭で遊ぶ子らを見ていると、小学校以降の理科教育につながっていると感じる。幼児期の原体験が、感性(センス・オブ・ワンダー)を豊かに鋭敏にするのだと思う。家庭による差がなく、共通体験として共有できることが、小学校側としてありがたい。


砂や泥でたっぷりと遊び、虫やカニやダンゴムシをつまんでつかまえ、花や葉を絞って色水をつくる。五感を刺激し、いろいろなものに興味をもち、好奇心や探究心を養う、すばらしい体験である。
小学校理科の単元で、園の保育とつながりの深いものを挙げてみる。
3年 春の自然にとびだそう たねをまこう 花がさいたよ 実ができたよ チョウを育てよう 風やゴムでうごかそう
4年 雨水のゆくえと地面のようす あつくなると さむくなると 生き物の1年をふりかえって
5年 植物の発芽と成長 花から実へ 流れる水のはたらき
6年 生き物のくらしと環境
笠原こども園での保育を見て、本校にも築山か流水実験場がほしくなった。時間が空いた時に手を付けようと思う。
地域との連携
岡崎会館から、会館だよりへの寄稿依頼があった。タイトルは自由だが、人権や共生に配慮した内容を心掛けた。800字程度の字数という指定だった。今回は、宮沢賢治で書くことにした。図書室からお目当ての本を探してきた。
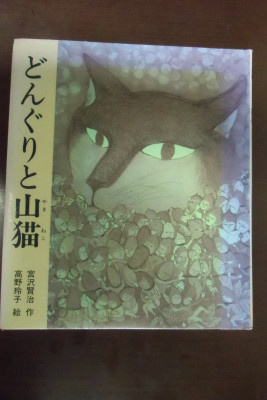
「どんぐりと山猫」(宮沢賢治)と笠原っ子
笠原小学校長 岡本 正彦
宮沢賢治の童話「どんぐりと山猫」が、私は好きである。
黄金色のどんぐりたちは、誰が一番えらいのかを山猫に決めてもらうために、三日間も裁判をしていた。「頭のとがりぐあい」「丸さ」「大きさ」「せいの高さ」などえらさの基準を各々主張し、山猫の仲裁は全く聞き入れられなかった。
一郎少年が助言したのは、「いちばんばかで、めちゃくちゃで、まるでなっていないようなのが、いちばんえらい。」ということだった。これでどんぐりたちを一分半で黙らせ、解決してしまう。逆説で論破しているように読み取れるが、賢治の詩「雨ニモマケズ」の中の「デクノボー」や、「虔十公園林」の「本当のさいわい」につながる、仏教的な教えや老荘思想を含んだ深い寓話なのである。
笠原っ子は、一年生から六年生まで学級編制がなく、同じ集団の中で成長する。衝突し、どっちが上なのかを争い、学級内で人間関係が固定化していき、それによって苦しくなってしまうことがある。大人から見れば、大した問題には感じないことでも、笠原っ子にとっては一大事である。私には笠原っ子が、黄金のどんぐりの姿に重なってしまう。
多様な価値観や基準のある中で、優劣を競いすぎることは、それほど大切ではない。「頭がいい」とか「走るのが速い」とか「力が強い」とか「絵がうまい」とかよりも、お互いのよいところをもっと認め合ってほしい。
先生たちも、基準を厳密にして優劣(成績)を付けることに、一生懸命になりすぎないほうがいい。小学校の成績だけで、その子の人生が決まるわけではないのだから。
笠原にとって、一番えらいのは、「ふるさとである未来の笠原を支える人」である。大人になっても笠原に住んで、地域を直接支える人もいるだろう。スポーツや勉学などに励み、笠原を離れて活躍する人もいるだろう。たとえ笠原を離れても、笠原を忘れず大切にする人は、やっぱりえらいと思う。
研修
院生のころ、高校の社会科の実践として大津和子さんのバナナの授業が話題になった。生徒にバナナを食べさせ、国際理解の学習へと発展していく。今の探究学習のはしりである。当時買った「一本のバナナから」という本を自宅の本棚から探したが、見つからなかった。実家の方かもしれない。
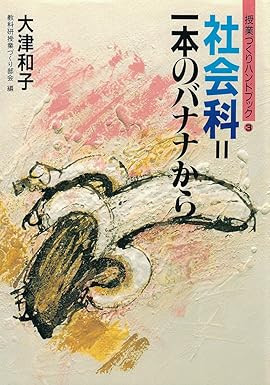
大津さんの実践が頭に残っていたので、バナナの木が教材になるかもしれないと思い、学校に持ってきたのだ。
「バナナと日本人」(岩波書店)という鶴見良行さんの書籍も話題になり、1980年代後半から90年代の初めごろは、バナナが社会科の教材として脚光を浴びていた。この本も持っていた。たぶん実家にあるだろう。
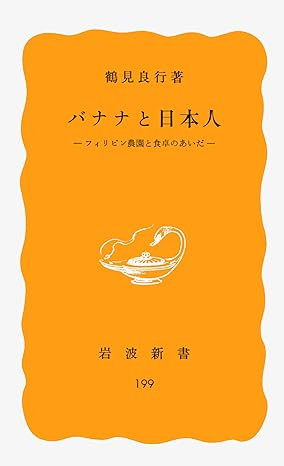
「バナナ」を切り口として、授業展開を組み立てていく大津さんの構想力が、私には魅力的だった。社会科の授業とは、こういうふうに作り上げるのだ、というコツのようなものをつかんだ。「教科書を教える」のではなく、「教科書で教える」授業は、今でも十分通用する。切り口は「バナナ」でなくてもよい。そんなダイナミックな「探究学習」を笠原をテーマにやれたらすばらしい。
例えば、「地球温暖化がこれ以上進んだら、笠原ではお茶のかわりにバナナを栽培したほうがいいか?」というテーマで、環境や経済を学べると思う。私が担任だったら、5年生の社会科か総合で10時間ぐらいの単元を構想するだろう。
バナナの木を、学校の花壇か農園に植えるだけではもったいないので、どこかの学年で教材に使ってもらえたら、うれしい。
研修
私の地元(磐田市豊田地区)の祭典では、「山下園芸」さんが、蘭の鉢を提供してくださり、毎年格安で販売している。今年は、蘭に加えてバナナの鉢もあった。
祭典の終わりになってもバナナの鉢が売れ残った。私が「学校に持っていくから買い取るよ。」と、1000円払うと、もう一鉢おまけしてくれた。1鉢500円は格安である。


子どもたちが登校する前に昇降口に並べて反応を観察した。

「あっ、バナナじゃん。」「これ、食べれるの?」「家の近くにもバナナを植えてあるとこある。」「すごく大きくなるよ。」
1~6年生で、反応を示したのは全部で9人。ほとんどの子は素通りしていく。
「バナナ」で探究学習を仕掛けようと思っている。